![]()
![]()
甘い、塩辛い、酸っぱい、苦い、辛いなど人間は色々な味を関知出来る。
従って好みも複雑に絡み合い、それぞれの生活してきた環境や、身体的な関わりの中で異なる。
「うまい」という言葉は「美味い、旨い、上手い、巧い、甘い」と書き表わされる。
これら「うまい」という言葉の意味について、「美味い」は、美=大きな羊=沢山食べられる。満足出来る。
食事が十分とれる。即ち、大きな羊は脂が乗り、おなか一杯食べられる。従って、美味しいという意味がある。
「旨い」は、ヒ=さじ、食事の道具。日=日にちと言う意味がある。
これは食事が出来る日の事を指し、今の日本の様に好きなものを好きなだけ食べられる時代では考えられないが、食べられる事に感謝し、食べ物をほめたたえる言葉であったと考えられる。
また「甘い」は、生体のエネルギ−摂取の素となる炭水化物(糖質)の味であり、ほとんどの動物はこの「あま味」を好み、身体にとって常に欲している栄養源の代表として、「あまいもの」は「うまいもの」として捉えられ、「うまい=甘い」と表記されたものと考えられる。
料理の味を褒める言葉で「甘味があって美味しい」などと表現されるが、これも甘い=美味しいもの、という観念的な表現の一つと考えられる。ドイツ語のうまいは『Schmackhaft』だが、これは、飢えが続いたと言う意味もあり、飢えたあとには何を食べても美味しいと感じる事から出来た言葉であろうと考えられる。
また、同じくドイツ語の旨味に相当する言葉『Wohlgeschmack』はWohl=幸福、ge=非分離動詞で結果、集合、完了などを意味する、schmack=飢えたの意味があり、これらを総合すると、飢えたあとの幸福を意味する。
これらを考えると、おなかが減っている時は何を食べても美味しいと感じるのは世界共通の言葉かも知れない。
余談になるが、1992年に仕事の関係で、アメリカのラスベガスやリノに行った時の事だが、カジノの中のレストランでは美味しいものは見つからなかったので、「アメリカで一番不味い場所はカジノのある所だ」と、友人に話した事がある。
理由として、カジノで勝った時は、どんなに不味いものでも美味しく感じ、カジノで負けた時にはどんなご馳走も美味しく感じられない。
それならばファ−ストフ−ドや見習い料理人が作った不味い料理でも営業出来るといった考えがあるのかも知れないと思ったからである。
近年ラスベガスもファミリ−アミュ−ズメントパ−クと化し、カジノを目的としていない人々も多数訪問しているというので、少しは味つけに気を使っているのかも知れないが、その後行っていないので分からない。
何れにしろ、味覚は単に舌のみで味わうものではなく、経験や周りの状況によっても大きく左右される事が、この事からも理解出来る。
明治41年(1908年)、日本の池田菊苗博士は昆布のうまい味について研究し、昆布のうま味の本体は蛋白質の組成成分であるアミノ酸の一つ、グルタミン酸1ソ−ダ塩である事を発見した。
それまで、味に対する概念は、甘味、苦味、酸味、鹸味の4味であったが、このグルタミン酸の味に「うま味」と名付け、全部で5味となった。学術的にもうま味は UMAMI と呼ばれている。
一般に、唐辛子や胡椒、山葵に代表される辛味については、痛みとして捉えられ、味を関知する味蕾を破壊すると考えられ、他の味覚とは区別されている。
『だしの会』では辛味の官能試験の結果、非常に辛いものを一定期間食べ、辛味に対して免疫力を持った場合では、辛味の中に隠された各種微妙な味についても関知する事ができ、他の味を十分感じられる事を考え合せ、辛味は非常に強い刺激をともなう味として考え、味には甘、鹸、酸、苦、旨、辛の6味があると捉える。
昆布
昆布の美味しさはグルタミン酸とマンニット、味の深みは他のアミノ酸類やミネラル分の複合体。
だし昆布としては、北海道道南沿岸で採取される真昆布、北部沿岸で採取される利尻昆布、道東北部羅臼町付近で採取される羅臼昆布、三石町付近で採取される三石昆布(日高昆布)などの、葉体が比較的厚い種類が多く使われる。
これらは、うま味の素であるグルタミン酸や甘味を持つマンニット、とろみのあるアルギン酸が多量に含まれている。
しかし、昆布の持つうま味は単にグルタミン酸や、アスパラギン酸などアミノ酸類の含有量の多さで決まるものではない。
自然界には、素材に含まれるグルタミン酸の重量比率を見ると、昆布などは比較にならない程多く含んでいるものも多い。
では、何故、昆布がだしとして有用なのであろうか。
昆布に含まれる成分は、種類だけでなく、季節や採取場所、採取時期によっても異なるが、一般的な天然真昆布の成分について調べてみると、海の中に生育している状態で、水分は約80%、灰分約5%、有機物約12〜15%、その他無機質などである。
だしとして使われる場合は海から採取したあと天日乾燥(最近は電気乾燥が多い)し、水分を蒸発させ、昆布の細胞膜を破壊し、表面を酢で拭き(殺菌、腐敗防止、柔軟化)さらに、2〜3年乾燥熟成を行ったものを使う。
表1からも理解出来るが、昆布は肉類、豆類、穀物類などと比べ、アミノ酸が含まれる蛋白質の量は取り分け多く含まれているわけではない。
真昆布と同じ蛋白質量のコ−ングリッツの組成を見ると、グルタミン酸量は、真昆布よりも若干多いが、アスパラギン酸は半分以下である。
食すると甘味は感じられるが、それ程強くはない。また、煮出してもだしとしてうま味を感じるエキスも感じられない。
この様に、うま味であるグルタミン酸の量だけでうま味を感じるものではない事が理解出来る。
それにも関らず、昆布はグルタミン酸のうま味を持つだし素材として、鰹節のイノシン酸のうま味と並び、和食のだしの双璧をなしている。
この秘密は、昆布がもつアミノ酸の種類やマンニット、アルギン酸などの量的バランスと味覚的バランスであると考えられる。
昆布に含まれるそれぞれのアミノ酸の味は、表2に示した通りである。これを見ると、うま味を呈するアミノ酸は、グルタミン酸、アスパラギン酸、アラニン、プロリン、セリン、メチオニンであり、これらのほとんどはうま味と同時に苦味や酸味、甘味も呈する。
甘味はうま味を補佐、強調し、苦味は味に奥行きやコクを感じさせてくれる。
さらに、昆布、ワカメ、カジメなどの特有成分であるアルギン酸はα−Dマンヌロン酸とβ−Lグルロン酸の重合体で、人体内では消化吸収されない物質(ダイエタリ−ファイバ−)である。
アルギン酸はとろりとした粘性と保水性を持つものである。
このアルギン酸が昆布のうま味を口中に留まらせているものと考えられる。
また、素干昆布表面に吹き出る白い粉状のマンニットと呼ばれる水溶性の甘味成分がある。
マンニットの甘味は昆布のうま味を補佐し、強調している。
この粉があまり多く昆布表面に噴き出しているものは品質管理が悪く、乾燥状態が良くないものとされる。
だしの会では、
1. 真昆布(北海道道南南茅部町産)
2. 利尻昆布(北海道利尻島産)
3. 羅臼昆布(北海道羅臼町産)
4. 日高昆布(北海道三石町産)
のそれぞれの昆布のだし汁についての官能試験を行った。
官能検査方法は、それぞれの昆布を4.5gの大きさに切り分け、別々に用意したpH7.0、硬度50の中性軟水600ccの中に10分間浸し、その後、中火で沸騰直前まで加熱し、火を止め、5分間放置後、試料の昆布を取り出し、だし汁を官能試験する方法をとった。
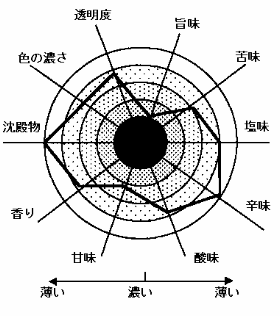 | 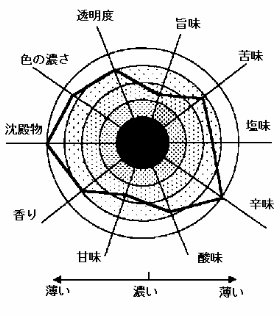 |
| 真昆布の官能評価グラフ だしの色:淡緑色の薄い色。 |
利尻昆布の官能評価グラフ だしの色:ほとんど無色透明に近い。 |
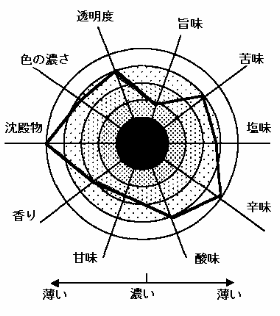 | 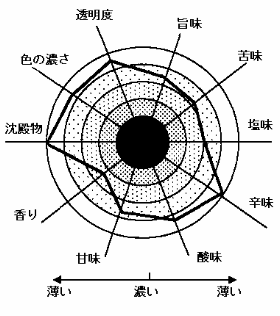 |
| 羅臼昆布の官能評価グラフ だしの色:淡黄色の薄い色、若干濁りがある。 |
日高昆布の官能評価グラフ だしの色:淡黄緑色の薄い色。 |